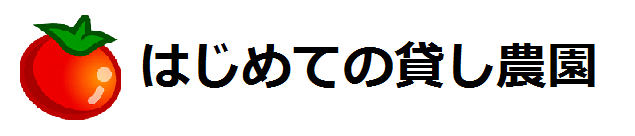フードコーディネーターの口コミや評判を知りたい人向けです。

食に関する資格でフードコーディネーターがあるけど、資格の評判や口コミはどうなんだろう。メリットとデメリットも知りたい。
フードコーディネーターとは、主に食品メーカーや飲食店でのメニュー開発や料理番組のサポートする資格です。
仕事をする上で必須な資格ではありませんが、知識とスキルがある資格として職種名にもなっていますね。
なかには資格を活用することで自分の料理教室を開講する方もいらっしゃいます。
では、フードコーディネーター資格はどのように役立つの?結局、使える資格なの?と疑問に思う人もいるでしょう。
そこで、今回は「【フードコーディネーターの評判】資格のメリットとデメリット」をご紹介します。
フードコーディネーターの口コミ・評判

資格を取得するかどうかで気になるのが、フードコーディネーターの評判。そこで、SNS上で調査をしてみました。
フードコーディネーターの良い評判
さらにフードコーディネーターの良い評判をみてみる
フードコーディネーターの良い評判を調査してみると、やはり食品関連の企業やレストランでメニューやレシピ開発をしている方が多いことが分かりました。
さらに、Twitterではフードコーディネーターの求人が見つかることもあり、需要があることも分かりました。
では、逆にフードコーディネーターに悪い評判はあるのでしょうか。
フードコーディネーターの悪い評判
次に、気になる悪い口コミ・評判を調査してみました。
フードコーディネーターの悪い評判をみてみる
フードコーディネーターの悪い評判を調査してみると「、3級を持っているだけでは意味ない」や「実務経験がないと使えない」「無駄」という意見がありました。
ごめんなさい、上記の口コミ以外に悪い意見は見つかりませんでした。。。
やはりフードコーディネーターの資格を持っていても実務経験や他の組み合わせる必要がありますね。
なお、フードコーディネーターの評判を調査していると、組み合わせる資格として食生活アドバイザー資格も取得しているという意見が目立ちました。資格の詳細は、下記のコラムを参考にどうぞ。
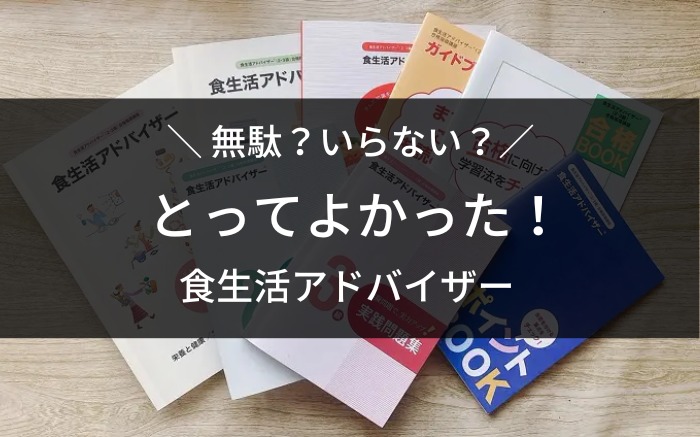
フードコーディネーターのメリットとデメリット

フードコーディネーターのメリットとデメリットは、下記のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| メニュー開発に役立つ テレビ番組などでコラボできる可能性も 求人の応募条件を満たせる | 学習費以外にも費用がかかる 仕事で活用なら2級以上が必要 資格試験が年1回しかない |
フードコーディネーターのメリット
ここでは、資格があればいいな、と感じたメリットを紹介します。
- 飲食店や食品関連企業でメニュー開発に役立つ
- テレビ番組などでコラボできる可能性も
- 求人の応募条件を満たせる
飲食店や食品関連企業でメニュー開発に役立つ
冒頭で紹介したYouTubeで紹介した方は、食品会社の勤務時代に資格を取得されていました。メニュー開発に携わる人にとっては取得しておきたい資格になっています。
テレビ番組などでコラボできる可能性も
食べるシーンがあるテレビ番組などでもフードコーディネーターが欠かせない存在になっています。例えば、映画で有名な「かもめ食堂」にもフードコーディネーターが関わっているそうです。
求人の応募条件を満たせる
フードコーディネーターの求人をみてみると、職種として応募がかけられていることがあります。フードコーディネーター資格があるだけ条件を満たすので応募がしやすくなるということも。
ただ、メリットばかりではありません。次に、デメリットもご紹介していきましょう。
フードコーディネーターのデメリット
次に、ここはイマイチだな、と感じたデメリットを紹介します。
- 学習費以外にも費用がかかる
- 仕事で活用なら2級以上が必要
- 資格試験が年に1回しかない
学習費以外にも費用がかかる
資格取得のための学習費以外にも、受験料や資格認定料が別途かかります。例えば、3級なら受験料11,000円、資格認定料21,000円が必要です。
仕事で活用なら2級以上が必要
フードコーディネーター資格には1級から3級まであり、仕事に関わるなら2級以上が必要と言えます。ただ、資格は独占業務の資格ではないので、それだけで仕事ができるわけではありません。
資格試験が年に1回しかない
資格の取得に必要な試験の合格ですが、試験日が原則として年に1回しかないので、学習のタイミングが大切になります。
なお、フードコーディネーターは意味ないかどうかについては、下記のコラムも参考にしてみくださいね。

フードコーディネーターになるには?

フードコーディネーターは、特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会が認定する民間資格です。
資格は、以下のように1級から3級に分かれています。
- 1級:プロとして活躍するための知識・技術
- 2級:専門的な知識と実践的な企画力
- 3級:食に関する幅広い知識
もしフードコーディネーターの2級または1級を取得するためには、まずは3級の合格が必須になっています。
では、資格を取得するにはどのような方法があるのでしょうか?
協会認定の学校に通って取得する
日本フードコーディネーター協会が認定する学校に通学し履修すれば、3級の資格認定試験が免除されます。
ただし費用もかかるので実践で学びたい人や1級・2級を目指している人におすすめです。
試験対策講座を受講し取得する
協会では各級ごとに試験対策講座が開催されているので、ポイントを絞って効率的に取得したい人におすすめです。3級なら例年10月に開催されます。
独学で資格を取得する
学習方法は市販されているテキストで学ぶこともできるので、特に3級は独学で取得することもできるでしょう。
資格認定資格対応の公式テキストが市販されているので、それを利用するのがおすすめです。
特に、3級は食に関する基礎知識が問われるので、テキストを徹底的に覚えれば独学でも比較的対策がしやすいでしょう。
なので、まずはフードコーディネーター3級の合格を目指しましょう。受験方式や費用などは、以下のとおりです。
| 資格名 | フードコーディネーター3級 |
|---|---|
| 認定機関 | 特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会 |
| 受験資格 | 3級:中学校卒業以上 |
| 受験形式 | 会場受験・CBT(Computer Based Testing)方式 |
| 試験日 | 通常11月頃(年1回) |
| 試験内容 | 「食」に関わる4分野。「文化」「科学」「デザイン・アート」「経済・経営」の知識 |
| 受験料 | 11,000円(税込) |
| 認定証等、発行料 | 21,000円(税込・認定登録料) |
| 難易度・合格率 | 未発表 |
実は、フードコーディネーター3級の合格率は発表されていません。
ただし、2級1次試験の合格率が約86%(2次は認定講座の受講)となっているので、3級は合格率は高く、それほど難易度は高くはないといえるでしょう。
フードコーディネーター資格については、特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会からどうぞ。
なお、フードコーディネーター試験について知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。

フードコーディネーターがおすすめな人

資格の取得におすすめな人は、以下のとおりです。
- 食品メーカーや飲食店でメニュー開発をしたい
- CMなどの撮影現場でレシピや演出に携わりたい
- フードライターとして食に関する記事を書きたい
- 料理研究家としてTVやYouTubeで活躍したい
- 料理教室やオンライン教室を開業したい
- ケータリングや出張で料理を仕事にしてみたい
特に、口コミや評判をみてみるとフードコーディネーターには資格に定義がないため、仕事内容が幅広く活躍されている方が多いようです。
この資格だけで仕事を見つけることもできますが、「複合的に他の資格を取得することでスキルを伸ばしていてチャンスを狙う」ことも必要であることが分かりました。
フードコーディネーターの評判まとめ
今回のコラムでは「【フードコーディネーターの評判】資格のメリットとデメリット」をご紹介しました。
フードコーディネーターの口コミ・評判から分かったメリットとデメリットは下記のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| メニュー開発に役立つ テレビ番組などでコラボできる可能性も 求人の応募条件を満たせる | 学習費以外にも費用がかかる 仕事で活用なら2級以上が必要 資格試験が年1回しかない |
資格の取得には費用もかかるので、フードコーディネーター資格を利用するベネフィットをよく考えましょう。